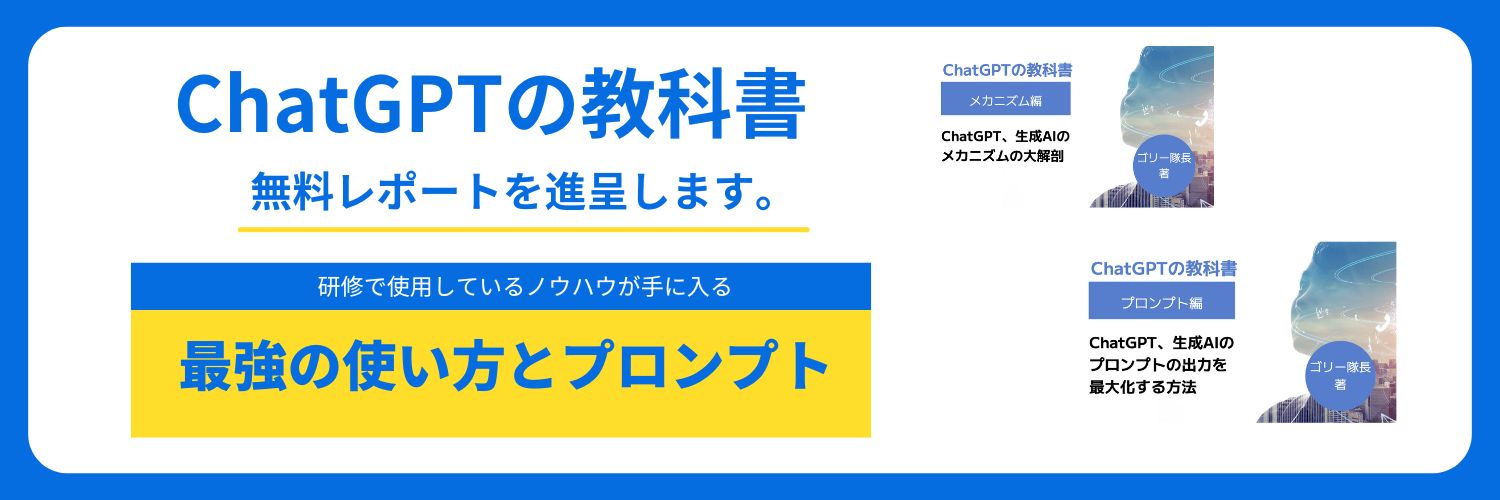
GAFAなどCEOはプログラマー出身!なぜシステム会社が儲かるのか?人を雇用するのは弊害が存在するので今すぐ仕組み化が必要!

世の中の潮流は4極化
世界的な流れとして、四極化です。
AIなどのシステムが出てきたことで次のような階層に分かれてきました。
- 仕組みを考える
- 仕組みを作る
- AI
- 仕組みの下で働く(ロボット)
今の仕事があるのは、日本人であるがゆえの日本語という言語の壁
日本語で仕事が通じるのは、日本人だからです。日本語が共通のフォーマットがあるからです。
世界では安い途上国への発注が当たり前
オフショア開発という低賃金の国への労働の移転が起きています。
アメリカでは英語圏ですので、システムやプログラミングに関しては、公用語が英語であるインドに発注が簡単です。アメリカ人が寝ている間にインド人が仕事をしてくれるので、開発サイクルも半分です。
高度なスキルを持つ人材は賃金が上がる
AIよりも上位の階層にいる「仕組みを考える」と「仕組みを作る」ができる人材は重宝されています。
「仕組みを作る」プログラマーは、低賃金で優秀な途上国にシフトしつつあります。
世界はフラット化しているので、単純作業は人件費は抑制される
マイクロソフトやDELL、Paypalといった国のコールセンターで片言の日本語の担当者に繋がったことはありませんか?
コールセンター業務も安い国へシフトしています。
- プログラミングは東南アジアにアウトソーシング
- 日本国内でもコールセンター業務は地方にシフト
人間はミスをするし怠慢な動物で雇うとリスクになる
人が作業すると、ムリ、ムダ、ムラ、ダブリなどが発生します。
どんな優秀な人でもこれらは起きてしまいます。
入力作業がまさにそうですが、人間な限りミスをします。ダブルチェックを行ってもミスは起こりやすいのです。
人を雇用すると
- 病気や事故などの欠勤リスク
- 社会保険などのコスト増
- 人によって能力差が出てくる
などが起きてきます。
人権意識や労働環境の保護が高まり、労力低減が必須に
Amazonでは、荷物をピックアップするのに人が移動すると人によってのスピードのばらつきや、歩くことで疲れるといった問題を抱えていました。
それを解決したのが、「動く棚ロボ」です。人が荷物がある棚に移動するのではなく、荷物のある棚がピックアップする人の前に移動する仕組みです。手間を省け効率化しています。
業績アップする会社はAIやロボットを使っている仕組み化している
プログラミングをすることは、仕組み化ができてしまいます。
仮にバグがあっても修正をすれば、「品質の均一化」が可能です。
CEOがプログラマー出身の例
GAFA+Mの創業者やCEOやプログラマー出身が多いです。
- Googleの親会社アルファベットのCEOのラリー・ペイジ
- AmazonやテスラモーターズのCEOのジェフ・ベゾス
- Facebookの創始者のマーク・ザッカーバーグ
- マイクロソフトの創業者のビル・ゲイツ
- オラクルの会長のラリー・エリソン
AIやロボットを使うと、人件費の削減や人不足の解消ができる
企業でも一部でも取り入れると、少数精鋭でマネジメントできます。
- 自動券売機(キャッシュレスにする)
- 製造ラインのロボット化
- WEBマーケティングで集客化する
- WEBを使って、動画や文字(PDF)で教育する
中小零細企業・中小企業でもAIやロボットを使える
プログラミングすると聞くと難しく聞こえますが、プログラミングができなくても、AIやロボットを使うことが出来ます。
仕組み化してAIやロボットを部下するポイント
AIやロボットの役割
- AIやロボットの役割とは、プログラムに判断基準や動作内容を予めセットしておくと、そのとおりにしてくれることです。
- AIはプログラミングに用いられ、ロボットは作業労働で使われることが多いです。
仕組み化には、AIやロボットを使って、自動化と半自動化を使うことです。
仕組み化では完全自動化と半自動化を使い分ける
仕組み化では完全自動化と半自動化を使い分けることがポイントです。
- 半自動化
- 完全自動化
- 半自動化:全自動洗濯機で、洗浄から脱水を行い、干すのは手動化する
- 完全自動化:全自動洗濯機で、洗浄から脱水、乾燥まで行う
- 半自動化:一般道路では運転して、高速道路では自動運転システムを使う
- 完全自動化:自動運転
半自動化から全自動化の仕組みを作る流れ
半自動化から自動化までは4つのステップで完成です。
ただしいきなり完全自動化はできません。そこで半自動化を導入してからシンプル化して自動化をしていきます。
①業務の流れを整理する
業務内容を整理するところから始めます。いきなり完全自動化しようとすると、人が行っている複雑な判断も自動化するために、むしろ手動の確認等で複雑化することもあります。
②半自動化でマニュアルや手順書を作る
誰でも再現できるようにマニュアル化しましょう。
- 専門用語を小5でもわかるように書く
- 手順をなるべくシンプルにする(3ステップ)
- 迷っても判断できるように判断基準を明確にしておく
焼き鳥屋で料理未経験の70歳を雇う場合
指示を明確にして誰でもできるようにする未経験者でも即戦力にできます。
- 串を指して
- 焼いて
- 音が鳴ったら上げる
ただし、このような単純作業もいずれはロボットにシフトされるかもしれません。おじいさんが焼いている方が味が出るので、あえて手動に残すのはありですね。
WEBでの半自動化の例
- 申込みや問い合わせがあった時に一度自動返信メールで受付を行い、後に手動で返信する。
③ムダ、ムリ、ムラ、ダブリを取る
ムダ、ムリ、ムラ、ダブリが出たら、その後に完全自動化を行います。
こちらの記事を御覧ください。
④全自動化の仕組みを作る
ムダ、ムリ、ムラ、ダブリが出たら、その後に完全自動化を行います。
この点は、コンサルタントや制作会社と相談してください。
その際には、シンプル化されたものが複雑化にならないように注意が必要です。
コンサルタントや制作会社では、自分の仕事を増やそうと複雑する会社や人もいるのも事実です。
WEBでの完全自動化の例
- お問い合わせ時の自動返信メール
- Googleフォームに入力すると、スプレッドシートに自動反映する
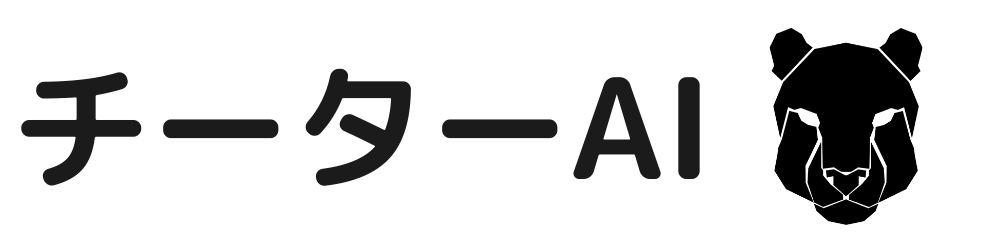
-20240306-7.001-812x457.jpeg)
-20240306-7.001-812x457.jpeg)